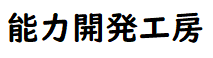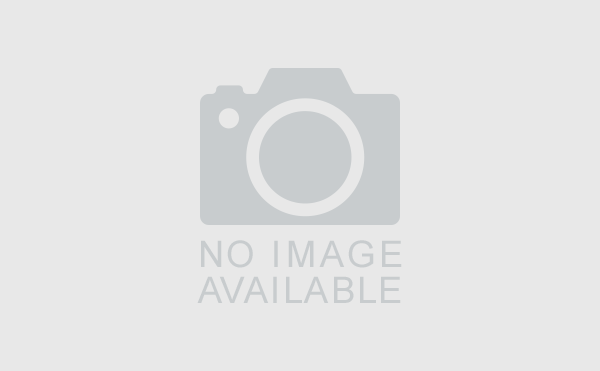2019年 センター試験英語第四問 構文解析講義2
ゆみこ:こんにちは
前回に引き続き2019年の英語のセンター試験の長文問題の構造解析に
取り組んでいきましょう。
第四問の第二段落です。
ラッコ:今日も頑張るぞー
ゆみこ:では、第二段落の最初の文です。
The researchers examined 140 paintings of family meals painted from the years
1500 to 2000.
ラッコ:これは、意味は分かるけど、the years 1500 のところが単語単位でどう修飾されて
いるのか分からなかった。
ゆみこ:確かに、the years from 1500 to 2000だったら分かりやすいけど、
from the years 1500 to 2000なのよね。
ここを文法的に解説するのは先生も降参です。
イディオムみたいなものだと考えて、先に行きましょう。
伊藤和夫大先生も文法の限界について話されていますし…。
ラッコ:いいんですか?
ゆみこ:いいんです。
では、解答をお願いします。
ラッコ:The researchers examined 140 paintings of family meals painted from the years
S ③ a → O ←ap a → n ← a ┯ –③ ← adp n
1500 to 2000.
n adp(paintedにかかる)
ゆみこ:paintedをfamily mealsにかけたんですね。
ラッコ:あれ? 変ですか?
ゆみこ:いや、おかしくは無いですよ。
私はpaintingsだと思ったのですが、「描かれた食事」でもOKですね。
ラッコ:驚かさないで…
ゆみこ:では、次に行きましょう。
These came from five countries: the United States, France, Germany, Italy, and the
Netherlands.
ラッコ:これは楽勝でした。
These came from five countries: {the United States}, {France}, {Germany}, {Italy},
S ① ← adp a → n n n n n
and {the Netherlands.}
+ n
それで、five countries とthe United States, France, Germany, Italy, and
the Netherlandsが同格ですね。
ゆみこ:ピンポン! この文は確かに簡単だったわね。
では、次に進みましょう。
The researchers examined each painting for the presence of 91 foods, with absence
coded as 0 and presence coded as 1.
ラッコ:実はcodeの意味が分からなかった。
ゆみこ:日本語のコード、あのグルグル巻いてある電気のコードなんかと勘違い
したんですか?
それはcordです。
ラッコ:スペルが違うのか。
ゆみこ:カタカナに引っ張られることは多いのよね。
すっかり馴染んでいるカタカナが、一番危なかったりします。
カタカナ英語こそ、辞書で確認が基本です。
ラッコ:へい。
ゆみこ:でも、最近はパーティーの案内なんかで『ドレスコード』って書かれていたり
するじゃない。
こっちはdress codeなんだけどな?
ラッコ:ふーん。パーティーに縁がないもんで… イジイジ…
ゆみこ:まあまあ、拗ねないで… 他には何かあったかしら?
ラッコ:これ、前半はいいとして、with以下が悩みました。
ゆみこ:でも、分詞構文だっていうのは、見抜けたんでしょう?
ラッコ:受験英語では、「withが来たら付帯状況の分詞構文を疑え」っていうのは
鉄則ですからね。
ゆみこ:へーそうなんだ。メモっておこう。
ラッコ:そうすると、構文解析はこうです。
The researchers examined each painting for the presence of 91 foods, with {absence
S ③ a → O adp n ← ap a n S’
coded as 0} and {presence coded as 1}.
P’ –③ ← adp n + S’ P’ –③ ← adp n
withが付帯状況を表す前置詞です。
つまりwith以下は副詞句で文全体を修飾しているってこと。
それと、for the presence of 91 foodsはexaminedにかかる。
ゆみこ:はい、OKです。
ここのS’とP’は、それぞれ主語と述語の関係にあることを表します。
でも、文の本当の主語と述語ではないので、ダッシュ(’)をつけて区別
しています。
さて、この分詞構文を普通の英文にするとどうなるでしょう?
ラッコ:Absence was coded as 0 and presence was coded as 1. かな?
ゆみこ:ちゃんとexamined にあわせてwasにしたのね。えらい、えらい。
ラッコ:エッヘン
ゆみこ:私はこの文が一番難しいかなって思っていたのだけど、結構あっさりクリアした
わね。
ラッコ:こういう型にはまった英文よりも、一見フツーの文が難しかったりするんだよ。
ゆみこ:なるほどね。じゃあ、詳しいらしいので、分詞構文の解説してもらおうかしら。
ラッコ:エエッ!! 僕、生徒だよ!
ゆみこ:しょうがないわね。
分からない方は、伊藤和夫先生の『ビジュアル英文解釈』の38の焦点か、
同じく伊藤和夫先生の『英文解釈教室入門』の付録の『別冊構文研究』の8を
読んでくださいね。
ラッコ:何? その伊藤先生に振っちゃうやり方は?
ゆみこ:紙面の都合上ね…
では、次に行ってみましょう!
For example, when one or more onions appeared in a painting, the researchers coded
it as 1.
ラッコ:これも、すんなり分かったな。
なので、いきなり解答です。
For example, 〈when {one} or {more} onions appeared in a painting〉,
adp n 節 a + a → S ① ← adp n
the researchers coded it as 1.
S ③ O adp n
ゆみこ:この文も簡単だったわね。
〈 〉でくくられた副詞節は、主文、この文だとthe researchers coded it as 1に
かかります。
for exampleは文全体を修飾していると考えて下さい。
あと、as 1の副詞句はcodedを修飾しています。
あ~ 手で矢印書きたい…。
ラッコ:多分、読者もそうして欲しいかもね。
ゆみこ:では、第二段落の最後の文に行きましょう。
Then they calculated the percentage of the paintings from these countries that
included each food.
これは、どうだった?
ラッコ:これも楽勝でしょう。
Then they calculated the percentage of the paintings from these countries
ad S ③ O ← ap n ← ap a → n
(that included each food).
S ③ a → O
( )の最初のthatは関係代名詞で、these countriesにかかる。
どうや!
ゆみこ:んんん? 訳というか、意味を考えないで構文だけ取ったでしょ?
ラッコ:なんで分かる?
ゆみこ:関係代名詞のthatを先行詞のthese countriesに変えて英文作ってみると、
どうなりますか。
ラッコ:These countries included each food.
訳は、「これらの国々は、それぞれの食べ物を含みます…」???
ゆみこ:先行詞はthe paintingsが正解です。
関係代名詞の先行詞は、必ず直前にあるわけではないのです。
だから、構文と意味と一緒に考えないといけないの。
まあ、初めの頃は、両方一緒に考えるのは難しいから、構文解析した後に意味を
考えて、それで辻褄が合うか確認するといいわね。
ラッコ:は~い。
ゆみこ:今回はここまでにしましょう。
前回同様、記号の解説について書いておきますね。
基本的には薬袋義郎先生の『英語リーディング教本』を参考にしていますので、
そちらも是非お読みください。
ラッコ:全部で4段落の文章だから、半分まできたかな?
ゆみこ:英文の分量的には、前半よりも後半の方が長いわよ。
でも、何を伝えたい文章なのかは掴めてきていると思うので、そういう意味では
半分を超えたかもしれないわね。
次回もお楽しみに~♪
構文解析の記号
主語 S
動詞 第1文型 ① 第2文型 ② 第3文型 ③ 第4文型 ④ 第5文型 ⑤
受動態の時は数字の前に「-」をつけて下さい。
目的語 O
補語 C
助動詞 aux
名詞 n
形容詞 a どの言葉にかかっているのか分かるように→で示すこと
形容詞句 形容詞句の始まりにある前置詞の下にapと記入し、それ以外の句の構成要素に
ついては、通常通り品詞を記入
副詞 ad どの言葉にかかっているのか分かるように→で示すこと
副詞句 副詞句の始まりにある前置詞の下にadpと記入し、それ以外の句の構成要素に
ついては、通常通り品詞を記入
接続詞
等位接続詞 +
等位接続の場合は、どれとどれが等位になっているのかを示すこと
{ }and { }
従属接続詞 接
形容詞節 ( )
副詞節 〈 〉
名詞節 [ ]