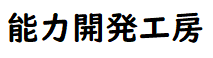C君の例
C君が最初に能力開発工房に来たのは高校2年生の10月でした。大学に行きたいと思っていましたが、学校の先生に、「どこも行くところがない」と、太鼓判を押されたとのことでした。聞けば、公立の中高一貫校に通っているとのこと。なおかつ英語に力を入れている高校だというのです。しかし、C君は英語は中学1年生の時に落ちこぼれていました。中学受験で燃え尽きたため、高校2年になるまで塾には行かなかったそうです。それどころか学校の教科書も高校に置きっぱなし、かろうじて試験前に持ち帰って勉強するだけとのことでした。
実際にどれくらい英語力があるか、2,3質問すると、中学レベルも出来ていませんでした。C君の場合は、受験まで1年半と期限が決まっていることもあり、月に3回のペースで通ってもらうことになりました。初めの頃は、勉強の習慣がなく、自宅で机に向かう習慣をつけるところからスタートするような有様でした。
中学、高校と勉強にはあまり前向きに取り組んでこなかったC君ですが、読書が好きで、大学では史学をやりたいという確固とした目標がありました。元々、知的好奇心はあるほうで、人の感情を慮る優しいところがありました。
小学生の頃から貧血があり、身体が丈夫ではなく、2時間かけて当塾まで通っていたのですが、時には着いた途端、青い顔で「少し休んでいいですか?」と言うなり、寝転がってしまうということも何回かありました。体力が無かったのも勉強を長時間続ける足かせになっていたようです。
能力開発工房の勉強方法は英語はもとより、古文も漢文も世界史も音読がつきものです。C君にも色々音読するように指示しましたが、全部は出来てなかったようです。イメージしながら音読することも、最初は早く終わらせたいとの気持ちが勝って、イメージすることよりも、早口で読んでしまっていたようでした。途中で何回か指摘し、イメージしながら音読するようにはなったのですが、大きな声で音読するのは、なかなか最後まで完璧にはできなかったようです。家族と一緒に住んでいるので、優しいC君は家族が、うるさくて迷惑になると思っていたのかもしれませんが…。
3年生の春からは古典と漢文と世界史の勉強も能力開発工房でみることになりました。
英語を始めたころは、勉強の習慣がついたら月2回のペースにする予定でしたが、4教科になったので、そのまま月3回のペースで続けることになりました。能力開発工房は、英語がメインの塾なので勉強内容は英語に絞って話を進めます。
大学受験まで残り少ない時期に中学英語を一から学ぶのは辛そうでした。周りの友達の使っている参考書を見て、不安を感じていたのでしょう。暗い顔で来ることも多かったです。コーチングで何度も基礎から学ぶ大切さを教え、帰るころにはやる気を取り戻して明るく帰っていくということが続きました。
また、この時点では、まだ中学英語の復習中なので、学校の英語の成績は伸びません。C君には、その内必ず伸びるからと説明して中学英語に取り組んでもらいました。しかし、学校の英語の先生が、あまりにも酷いC君の成績を案じて、次の文法テストが悪かったら補講しようと申し出て下さったのです。とても生徒思いの有難い先生だと思うのですが、補講に時間を取られると、ただでさえ時間がないのに能力開発工房で指示している勉強をする時間が無くなることは目に見えています。そこで仕方なく、策を講じました。文法のテストに出るところは決まっていて、勉強しているテキストの内容そのままとのことなので、そのテキストの英文を解析して暗記してもらうことにしました。この当時、C君が独力で解析できる能力は、まだありませんでしたので、子供の宿題を肩代わりする親のように、こちらでちょっと手伝ってしまいました。本当は良くないのでしょうが…。そんなズルをして(しかし、暗記はC君が頑張りました)、補講を免れることができました。それと同時に解析することで、今まで分からないまま適当に丸暗記していた文法の問題が、解析して理解すれば、頭に残ることも分かってもらえました。文法問題の選択肢を適当に選んで、当たったり当たらなかったりするのがテストだと思っていたものが、答えを選ぶときに理由に確信を持てるという経験をすることで、自分でも分かってきたという実感が出たそうです。このことで、能力開発工房の勉強方法を心の底から信頼してもらうことが出来ました。
『英文解釈教室入門編』を5回繰り返しました。問題文を解析して提出してもらうのですが、最初の頃は、間違えていたり、分からないまま提出されていることが多かったです。提出前に本の解説を読んで、自分なりに訂正したものを提出してもらうのですが、伊藤和夫先生の懇切丁寧な解説にもかかわらず、間違えた解析のまま提出されていました。回を重ねるごとに、提出する解析の精度もあがってきました。
3年生の夏休みに、C君にティーンズ向けの洋書にトライしないかと言うと、本が大好きなC君は目を輝かせました。C君は英語の本を読むなんて自分とは遠い世界だと思っていたのが、このまま英語の勉強を続ければ洋書を読めるようなることを実感したようです。
『英文解釈教室入門編』は大分理解できてきたようなので、『ビジュアル英文解釈』に進むことにしました。もう受験まであとわずかしかありません。しかし、最後まで英語の底力を上げて勝負することを選び、『ビジュアル英文解釈』に進みました。
学校でも英語落ちこぼれで通っていたC君ですが、3年生の2学期後半、とうとう学校の英語の成績も上がり始めます。友達に「長文読解を教えてくれないか」と、言われるようになったと、嬉しそうに報告してくれました。本当に良かったです。
1月に入れば、学校も休みなるので、そこで最後のラストスパートをかけようと考えていたのですが、学校の都合で授業が1月の中頃まであることになりました。そうすると、また予定が狂ってしまいます。受験だからと言って、集中講義をやる予定はなかったのですが、そんなこんなで間に合いそうにありません。仕方なく、最後の奥の手で、正月をはさんで集中講義で『基本英文300選』を解析し、音読する講座をつきっきりでやりました。なんせ、解析を家でやってもらって、それがちゃんと出来ているか確認する時間がなかったのです。弁当を持ってきてもらって全部で朝から晩まで5日間かかって全てを解析し音読しました。C君は体力があまりないのに、本当に頑張ったと思います。
受験直前には、最初のころの受験を他人事のように感じているような幼さはなくなり、大学で勉強するんだという主体性が出てきました。
実際のところ、受験勉強は予定したところまで全く進まなかったので、希望する大学どころか、その下のランクでも合格しないのではないかと危惧していました。しかし、第一希望のJ大学は落ちたものの、R大学とG大学の史学科に合格することができました。後日、C君が高校に「R大学に行くことを決めた」と、報告に行ったところ、先生方も友人も「おめでとう」の前に、驚かれたようです。「どこにも行く大学はない」と太鼓判を押されたC君が、R大学に行き、周りの生徒の多くは、C君以下のランクの大学か浪人がほとんどだったのですから…。