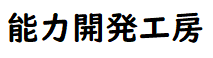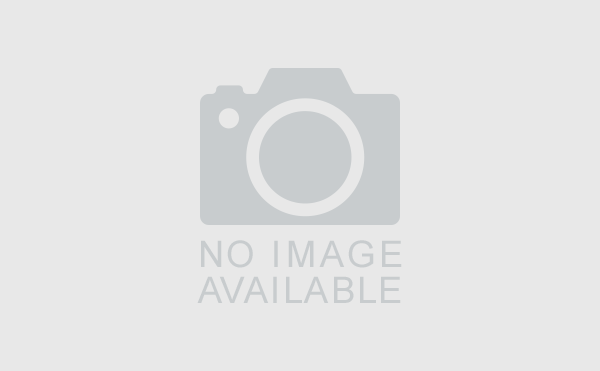効率よく勉強するとは?
効率よく勉強するとは? (ユミコ)
「効率よく●●をする」という言葉は、よく聞きますよね。勉強を効率よくできたらいいなって思っている方も多いと思います。何かをマスターする時に、最速で行くやり方があれば、それでマスターしたいと思うのは当然でしょう。
ただ、この「効率よく」という言葉を勘違いして使っている方がいるようです。どういうことかと言うと、「効率よく」と書いて「楽をする」と読む状態になっている。
英語の場合で説明しましょう。ビジュアル英文解釈をマスターするためには、テキストの英文を音読することが必要です。多くの人にとって面倒くさい作業です。そこに、「これって勉強方法として非効率だよね。もっと効率が良い方法ないかしら?」と悪魔のささやき(?)がくるわけです。「音読の回数を減らして、もっと早く終わらせた方がいいんじゃない?」と考えたりする。
これは「効率が良い」のではなくて、「楽を求める」ですよね。
もし、「効率」という言葉通り行動するならば、一つの努力で多くの結果に結びつくことを意図するわけです。音読する時に、1回1回を大切に音読する。つまり、英文で書いてあることをしっかりイメージする。音読して分からない時は再度テキストを読んで理解する。この方が最終的には理解が進むわけで、本当の意味で効率が良い勉強方法だと言えるでしょう。
しかし、楽を求めて音読の回数を減らす。それどころか、音読そのものを一度もやらずに先に進んでしまう。そうすると、確かに早くテキストの最後のページにたどり着けるでしょう。でも、そのテキストの内容を理解して覚えているでしょうか?
効率のよいやり方という楽な道をいつも模索していると、そのために費やした時間の方が多くなるだけで、まったく何も進んでいなかったということになりかねません。
巷には「聞き流すだけで英語が身に付く教材」などが売っています。聞き流すだけでと言われると、時間の有効活用できる気分になります。しかし、要はテキストを見て、分からない単語を一つ一つ調べて、文法の不明な点があれば、参考書や辞書で確認し、その上で音読したり、暗唱したりする手間を省きたいというズルい気持ちを「時間の有効活用」というポジティブなイメージを持つ言葉に置き換えているだけです。
もっと効率の良いやり方があるんじゃないだろうか?と思った時は、本当の意味で効率化なのか、それともズルさの言いかえなのかを見極める必要があると思います。
そして、ズルさに気が付いたら、勉強に王道なしという言葉を胸に刻んで進みたいものです。