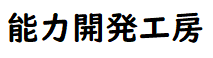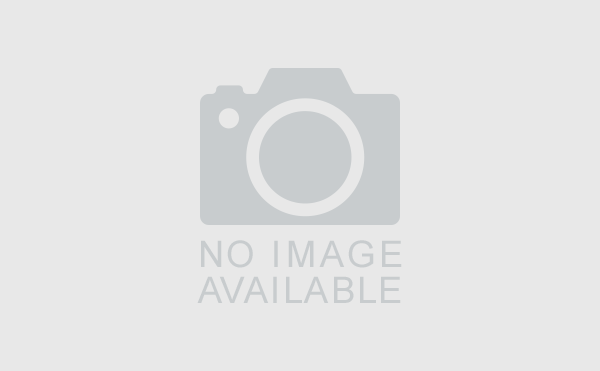構文解析の重要性について
構文解析の重要性について
早速ですが、次の英文を読んでください。
What you put your attention on grows.
これはルイーズ・ヘイの『You can heal your life』という本の中の小見出しの一文です。小見出しなので、途中にあるとはいえ、前からの文脈がなくてもスッとわかるはずの文です。しかも、単語は中学校レベルです。この文の意味と文の構造どれが主語で、どれが述語か等)分かりますでしょうか?少し考えてしまった方や、分からなかった方もいるのではないでしょうか。そして、分からなかった場合、どこが分からなかったか言えますでしょうか。
もし、分からなかったとしても、構文解析しようとすると、何が分からなかったのかが分かります。知らない単語があったのか、put とgrowsのどちらがメインの述語か分からなかったのか、on は一体何なのかが分からなかったのか、それともwhatで始まる関係代名詞の名詞節が分からなかったのかが浮き彫りになります。
そんな七面倒なことしなくても、英語はできるようになるんでしょう?という声が聞こえそうですが、どうして英文解析が大切なのか解説しますので、ちょっと長くなりますが、興味のある方は最後までお付き合いください。
英語の勉強方法は沢山ありますが、どんな勉強方法でも大切なことは、自分がどこまで分かっているのかを理解しながら進むことではないでしょうか。ここで「分かっている」というのは、「今は理解できていないことが分かっている」ことを含みます。
参考書に書かれていることや先生の話を全て理解できていなくても、理解できていないことが分かれば、そこを理解するために他の参考書を読んでみたり、先生に尋ねてみたり、もしくは保留にして先に進み後で戻ることもできるでしょう。
英語の勉強で躓く一番の問題は、何が分かっていて、何が分からないかを自分で把握できていないことです。そこが分からないと、何をどうやって勉強したらいいのか分からないので、断片的に耳に入ってきた情報に踊らされて、自分の実力に合っていない勉強をしてしまったり、力にならない勉強方法に手をだしてしまったりしがちです。そして、勉強に時間をかけた割には思ったように伸びが実感できないということになってしまうのです。
薬袋義郎先生の『英語リーディング教本』にも「シュリーマン流の音読、暗唱さらにシャワーのように英語を浴びるといったやり方を実践しているのに、思うように効果をあげられないで困っている方が多い」と書かれていました。
私も英語の音読をしたり、『どんどん話すための瞬間英作文』を暗記したけれども、一向に英語力がつかなかったという人を知っています。(そもそも瞬間英作文は暗記用の本ではないのですが…)
どちらも勉強法そのものが悪かったわけではありません。むしろ、英語を学んでいくうえで、音読も日本語を即座に英文に変換するトレーニングは必要なことです。それならば、何故、英語の実力がつかなかったのでしょうか。
その方は、音読した英文の和訳は知っていたでしょう。それで本人は英文が分かったつもりになって音読した。でも、構造つまり文法が分かっていなかったので、丸暗記になってしまった。
丸暗記の場合は、やり続けないと忘れてしまいます。また、丸暗記した例文と全く同じフレーズを使う機会というのは、めったにないものです。自分が伝えたい内容に合わせて、暗記した文に少し変化を加える必要が出てきます。しかし、変化を加えたくても、文法が分からないと、どこをどう変えたらいいのか分からず、結局使えないという結果になってしまいます。
例えば、日本語の「私は学校に行きます」という文の主語を変えてくださいと言われれば、「あなたは学校に行きます」とか、「彼は学校に行きます」と変えることが出来るでしょう。意識しているかどうかは別として、文法として主語が何かを分かっているからです。この文は簡単な文なので、そういう知識がなくても出来てしまうかもしれませんが、もっと難しくなると、分からなくなってしまいます。
しかし、最初から構文解析をしながら勉強していれば、何が不明なのか分かったはずです。構文解析は、「分かっているのか」、「分かっていなのか」を判断する杖になってくれます。
実は、私も同じような体験をしています。昔、伊藤和夫先生の『ビジュアル英文解釈』を勉強し始めた時、構文解析のやり方を知りませんでした。英文を和訳して、その後解説を読み、音読をしていました。解説を読んだ時は、分かったつもりになっていたのですが、本当は理解していなかったのでしょう。『ビジュアル英文解釈』の勉強を進めても、洋書が読めるようにならなかったのです。
その後、薬袋義郎先生の『英語リーディング教本』を読み、構文解析のやり方を知りました。『ビジュアル英文解釈』の勉強方法に構文解析を取り入れたところ、自分が理解できている所とできていない所がハッキリと分かるようになりました。
分からない所は、持っている参考書を片っ端から読みました。同じ項目でも参考書の著者によって微妙に説明が違います。1冊目で分からなくても、2冊目や3冊目の参考書の説明が自分にしっくりときて、理解できるようになることは多いものです。(多分、これは英語の勉強に限ったことではないかもしれませんが…)
また、何冊も参考書を読むことで、英語の例文を沢山見ることになりました。それによって、説明と例文がリンクされ、自分の中で腑に落ちる感覚が得られました。お陰で、次に同じような英文構造の文が出てきたときは、見抜けるようになりましたし、洋書も読めるようになってきました。
このように、英文が簡単だったり、和訳や解説を読んで分かった気になるケースも多いですが、もう一つ背景知識で読めた気になってしまう場合もあります。
日本語でも英語でも論理が破綻している文章というのは、あり得ません。例えばTOEICのテストで会社のピクニックの話の途中でコピーの紙の発注先が変更になった話に変わり、更に、来週はエレベーターの工事がある案内に変わって、また最後にピクニックの話に戻る文章が出ることは、あり得ませんよね。
そうすると、ピクニックの話ならピクニックに関連する事柄を知っていれば、英語が多少読めなくても、多分こういうことを言っているのだなと予想出来てしまう。ピクニックのような皆に馴染みのある事柄でなく、一見難しい話でも、その内容を熟知している人にとっては、内容を予想するのは簡単です。
実際、以前一緒に勉強していた外資の金融マンは、英字新聞を読んで、何が書かれているのか把握していましたが、それは、英語の構造がしっかり把握できているからではありませんでした。金融マンの方の得意分野の話だから、単語を繋ぎ合わせて理解していたのです。
その方は、背景知識を頼って英文解釈していることに気づき、英語の構造を理解する勉強方法を探して薬袋義郎先生の『英語リーディング教本』にたどり着きました。そして、私にもその本を紹介してくれたのです。
しかし、この方のように内容についてのテストに全問正解しているのに、本当は構造が取れていないと気づくのは難しいことです。そして、分かっているつもりで先に進み、いつか新しい分野の本を読もうとしたとき、単語を調べても読めない日がやってきてしまうのです。
ちょっと脅しになってしまったようですが……。 要は、日本語の本なら新しいジャンルの内容でも一から把握できるように、英語で背景知識の無い本を読むためには、英単語もさることながら英文法(構文解析)の力が不可欠なのです。
今まで英語を勉強して、テスト等の答えは当たっていても内容の理解に100パーセント自信が持てなかった方は、構文解析の勉強が効果的です。また、これから英語を勉強しようと思っている方も、最初から構文解析をしながら勉強していけば、いつも自分が分かっているかどうか自信を持って進んでいけますよ。